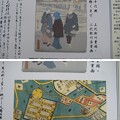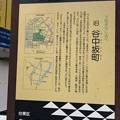11.03.14.鷲神社(浅草 お酉様)(台東区千束)
- 91
mixiアルバム「鷲神社(浅草 お酉様)(台東区千束)・酉の市」コピペ――
https://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000051232633&owner_id=32815602
2012年02月22日 13:59
11.03.14.
おおとりじんじゃ。
別称、鳥の社、御鳥(おとり)ほか。
御祭神、天日鷲神(あめのひわしのかみ) ・日本武尊(やまとたける)。
御神徳、天日鷲命は、開運、殖産、商賣繁昌が高い。日本武尊は、勝運、武と志に高い。
起源は現在隣接する長国寺に祀られていた鷲宮に始まる。明治の神仏分離令により長国寺が離れた。
※酉の市――
「花園神社/浅間神/酉の市/※アメブロリンク」→http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000031936906&owner_id=32815602
かつては「酉の祭(とりのまち)」と呼ばれていたが、次第に「市」の文字があてられていった。祭に市が立ったということ。酉の市(酉の祭)は、鷲神社御祭神の御神慮を伺い、御神恩に感謝し、来る年の開運、授福、殖産、除災、商売繁昌を祈願する祭事である。
かつて社号は鷲大明神社と称した。元来 鷲大明神社の「大」は敬意、「明神」は神を奉る号。東都歳時記には、「酉の日・酉の祭、下谷田甫(したやたんぼ)鷲大明神社当社の賑へることは、今天保壬辰(1832)より凡そ六十余年以前よりの事」とあり、宝暦・明和年間(1750〜60)にはすでに酉の祭は相当な賑わいで、それ以前から年中行事として行われていたことがわかる。
宝井其角(松尾芭蕉の弟子)の句に「浅草田甫・酉の市」として、
春を待つ ことのはじめや 酉の市――
とあり、酉の市は霜月(11月)に入って最初の市立てで、正月(1月)が近づいてきた事を詠んでいる。もう暮れか、正月の支度を揃えるか、などを歌っている?
酉の市の始まりは、江戸近郊に位置する花又村(現 足立区花畑にある大鷲神社)であるといわれ、祭りの形態も、当初は近在の農民が鎮守である「鷲大明神」に感謝した収穫祭であったと伝えられている。祭りの日、氏子たちは鷲大明神に鶏を奉納し、終わると集まった鶏は浅草の浅草寺まで運び、観音堂前に放してやったといわれる。
当初武士の参詣が多かったと伝えられているが、やがて江戸市中からは武士だけでなく、町人がこぞって参詣するようになった。社前では年末の一発勝負を賭けた辻賭博が開帳され、にぎわったそうだ。しかし、安永年間に出された賭博禁止令から、その盛況は浅草へと移っていく。
当時、花又村を“本の酉”、千住にある勝専寺(赤門寺)を“中の酉”、長國寺が別当をつとめていた浅草の鷲大明神を“新の酉”と称し、この3ヶ所の酉の市が有名だった。
浅草長國寺の“新の酉”は、東隣に新吉原が存在していたこともあり、鷲妙見大菩薩(鷲大明神)が長國寺に迎え移され祀られた明和8(1771)年頃から一躍最も高名な酉の町として知られるようになり、今日に至っています。
※酉の市の名物、縁起熊手。金銀財宝を詰め込んだ熊手で、幸運をかきこむ、幸福をはきこむと言って開運招福、商売繁盛を願った。
※境内には、宝井其角句碑、正岡子規句碑、樋口一葉文学碑・玉梓乃碑がある。
※ちなみに。神使としては
烏(熊野三山)
鶴(諏訪大社)
鳩(八幡宮)
鷺(気比神宮)
鶏(伊勢神宮)
と御座します…f(-_-;
以前アップ済
http://photozou.jp/photo/show/650854/231617648
〜
http://photozou.jp/photo/show/650854/231617666
何枚かフォト蔵に消されました┐(-_-Ξ-_-)┌
アルバム: 東京都2台東区/武州江戸
お気に入り (0)
まだお気に入りに追加している人はいません。
コメント (0)
まだコメントがありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントするにはログインが必要です。フォト蔵に会員登録(無料)するとコメントできます。